研究部
第二研究グループ
日本とアジア諸国が政策立案のために相互から学べる経験
日本はアジアで最初に現代の先進国になった国で、様々な成功と失敗を経験してきたが、成長しつつあるアジア諸国にとって、いずれも貴重な参考になる。この領域では、日本の重要な経済協力パートナーとしてのアジア新興国が日本の経済発展過程・関連政策から何を学べるかについて調査研究を行い、研究成果に基づいて政策提言を行う。
また、現代はもはや欧米のみから制度改革の洗礼を学ぶ時代ではなくなっている。この領域では、日本が近年成長著しいアジア諸国のダイナミックな経済成長と関連政策から何を学べるかについて調査研究を行い、研究成果に基づいて政策提言を行う。
| グループ長 | 岸本 千佳司 |
|---|---|
| メンバー | ドミンゲス・アルバロ |
基本プロジェクト2025

本研究の代表者は、過去数年間に一連の台湾のスタートアップ・エコシステムに関する研究プロジェクトを実施してきた。とりわけ、スタートアップを支援するアクターの事例研究を積み重ねてきた。例えば、アクセラレータ(AppWorks、StarFab Accelerator、Epoch Foundation & Garage+)、大企業(Wistron)、大学・研究機関(工業技術研究院、台湾大学創創センター、交通大学産業アクセラレータ)、政府・公的機関(新竹科学園區、高雄市)に関する研究である。R7・R8年度プロジェクト(2年計画)では、これらの研究成果を踏まえ、台湾のスタートアップ・エコシステムの発展状況を体系的に分析することを目指す。1年目(R7年度)は、これまでの研究の延長線上で、手薄な部分を補強していく(例えば、資金提供者=VCやエンジェル投資家クラブの事例研究、など)。2年目(R8年度)は、これらの成果を踏まえて、エコシステム全体を俯瞰し、その全体的な発展状況を分析する予定である。
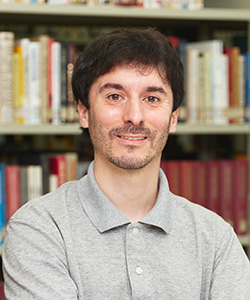
中国の急速な経済成長と産業の拡大は深刻な大気汚染を引き起こし、公衆衛生への影響が懸念されている。本研究では、Wu et al. (2022) のデータセットを拡張し、より多くの都市とより長い期間を含めた新しいデータセットを用いて、所得と大気汚染の関係を分析する。空間分析手法を用いて、所得の増加が大気の質を改善するかどうかを評価し、空間的な波及効果を考慮に入れる。さらに、人口密度を補正することで、人口動態や経済的要因の影響をより適切に分離し、地域間の格差が存在することを考慮する。拡張されたデータセットを活用することで、従来の研究結果がより多様な都市環境や長期的な視点で妥当性を持つかどうかを検証する。また、大気汚染と所得の格差が拡大しているのか、それとも収束しているのかを分析し、中国の現在の発展の環境持続可能性についての洞察を提供する。本研究の結果は、経済成長と環境保護のバランスを取るための政策的示唆を与えることができる。
