研究部
第一研究グループ
アジアー日本間の経済関係と現代的課題
日本とアジアとの結びつきやグローバル化など経済環境変化への対応に関する政策課題に焦点を当てて、その発生メカニズム・経済影響に関する学術研究を行うと共に、国内外の研究者と連携してアジアの共同発展に資するための政策研究を行う。研究テーマとしては、アジアと日本の間の人・物・資本等の移動からみた相互依存関係や国際情勢など近年発生した経済社会環境変化への対応策について学術研究と政策研究を推進していく。
| グループ長 | 本間 正義 |
|---|---|
| メンバー | 柯 宜均 |
| グエン・フン・トゥ・ハン |
基本プロジェクト2025

日本、韓国、および台湾は、いずれも戦後に著しい経済成長を遂げた国と地域である。その原動力は市場を世界に求め、比較優位に基づき国内の産業構造を転換させてきたことにある。その過程で、農業は比較優位を失い、各地域とも輸入が増加し食料自給率は低下した。しかし、経済発展の初期においては、農業は搾取されつつも工業部門に労働と資本を提供し、工業化の礎を作った。しかし、経済発展が進むにつれ、農業は保護される産業に転換していく。本研究では、これらの地域における経済発展と農業政策の関係を歴史的に調査し、その変遷の本質を探り、今日のこれら地域の農業のあり方の是非を問い、また今後どのように発展すべきかを検討する。
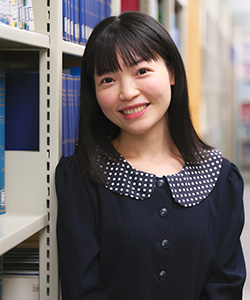
気候変動による異常気温は、健康への悪影響につながっている。エアコンのような家庭用温度調節装置が健康リスクを軽減する一方で、エネルギー価格の上昇は低所得者の利用を抑制する。この研究では、住宅用太陽光発電(PV)の設置がどのように健康リスクを軽減するのか、またそのメリットが所得層や地域によって不平等に分配されるのかどうかを検証する。具体的には、日本の死亡率に関する地域レベルのパネルデータを用いて、住宅用太陽光発電(PV)の設置による健康リスクの軽減効果とその格差を計測する。この研究は、再生可能エネルギーの利用メリットと格差の両方を評価することで、気候変動への適応と社会的公平性のためのバランスの取れた政策の策定にエビデンスを提供する。

本研究は、発展途上国においてエネルギー貧困が子どもの主観的な幸福度にどのような影響を及ぼすのかを解明し、重要な研究ギャップを埋めることを目的としている。現在、世界中の約7億7千万人が電気にアクセスできず、26億人が清潔な調理用燃料を利用できない状況にあり、エネルギー貧困は健康、教育、経済的生産性を損なっている。この影響は特に子どもたちにとって深刻である。
本研究では、Young Livesプロジェクトのデータを使用し、エネルギー貧困を多次元的な指標で測定するとともに、子どもの幸福度を主観的な生活満足度スコアで評価する。また、電気料金を操作変数(Instrumental Variable)として利用した二段階最小二乗法(2SLS)回帰モデルを用い、因果関係を検証する。
この研究の成果は、エネルギー貧困がもたらす有害な影響を軽減するための政策立案において、政策決定者に貴重な知見を提供することを目指している。
